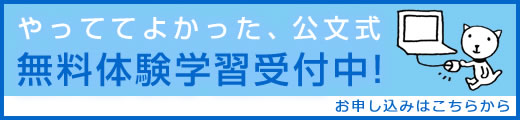絵本作家インタビュー
vol.11 絵本作家 黒井健さん(前編)
絵本作家さんや絵本の専門家の方々に、絵本についての思いやこだわりを語っていただく「ミーテカフェ インタビュー」。今回は、『ごんぎつね』『手ぶくろを買いに』などでおなじみの絵本作家・黒井健さんです。優しく柔らかなタッチの絵で“色鉛筆の魔術師”とも呼ばれる黒井さんは、NPOブックスタートの理事としても活動されています。そんな黒井さんに、絵本作家になったきっかけや絵本制作におけるこだわり、読み聞かせの心得などを伺いました。
今回は【前編】をお届けします。 (【後編】はこちら→)

黒井健(くろい・けん)
1947年、新潟県生まれ。新潟大学教育学部中等美術科卒業。学習研究社幼児絵本編集部を経て、フリーのイラストレーターとなり、絵本・童話のイラストの仕事を中心に活躍。1983年、サンリオ美術賞受賞。主な絵本作品に『ごんぎつね』『手ぶくろを買いに』『猫の事務所』(いずれも偕成社)、「ころわん」シリーズ(ひさかたチャイルド)など。画集に『ミシシッピ』(偕成社)、『ハートランド』(サンリオ)などがある。2003年、山梨県清里に「黒井健絵本ハウス」を開設。NPOブックスタートの理事も務める。http://www.kenoffice.jp/
編集者として足を踏み入れた絵本の世界

子どもの頃から、手先は器用だったんでしょうね。図工は小学校の頃からずっと5。家庭科も5でした。 中学生の頃の夢は、円谷プロに入ること。当時は模型をつくるのがすごく好きだったんです。夏休みの課題で軍艦の「武蔵」や法隆寺五重塔を、キットを使わずにつくっていました。法隆寺五重塔の欄干の部分はとても大変で、夏休み中かけて、泣きながらつくったんですよ。大変な思いをしましたが、新潟市から賞をもらいました。
大学受験では、グラフィックデザイナーになりたいと思って美大のグラフィック科を受けたんですが、うまくいかず、中学の美術の先生になるような学科に入りました。でも教師になる気はなかったので、卒業後、あてもなく東京に出たんです。グラフィックデザインをやりたくていくつも会社を受けましたが、どこも採用してくれなくて……絵のそばで仕事をしていられればいいやと思ったときに出会ったのが、学習研究社でした。
学研に入社して入ったのが、絵本の編集部。保育月刊誌の編集の仕事でした。それまで絵本のことは全然知らなくてまったく興味もなかったんですが、そこで初めて絵本の世界にかかわるようになったんです。作家さんに会って話を聞けるのはうれしかったですね。「画材はなんですか?」とか直接聞けるから。「こういう企画で、こんな絵ができるんだ」って驚きもありますしね。その頃はいろんな作家さんに会って、いろんな質問をしました。
その後、一日中絵を描いていたいという思いで会社を辞めてフリーになりました。その当時はファッションイラストレーターになりたくて、イタリアのファッション誌ばかり見ていたんですが、「黒井くん大変だろうから、これでも描きなさい」と学研から仕事をもらうようになって。高校雑誌、週刊誌、百科、中学雑誌、幼児向け雑誌、女性雑誌など、いろんなところでイラストを描きました。1センチ5ミリ角の見出しの上のカットとかから始まって、だんだん3センチになり、4センチになり、そのうちに、「じゃあこの付録の表紙描いてみる?」って。絵本のデビュー作も学研の保育月刊誌でしたね。
すべてを変えてくれた『ごんぎつね』
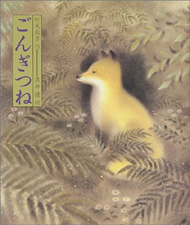
▲『ごんぎつね』(新美南吉・作、偕成社)
絵本の絵を描くようになってからも、苦労はしっぱなしでした。今でもよく覚えてるのが、「子どもが縄跳びしてるカットを描いてください」と言われたときのこと。縄跳びって、跳んでるときは縄はどこにあるんだ? 持つ手はどんな風になってるんだ?って、わからないことだらけで。自分の手を見ながら描いたら、かわいい女の子が私のごつい手で縄跳びしてました(笑)
それでもその後、どんどん仕事が忙しくなって、年間16冊くらいの絵本の絵を描くようになったんです。ひと月に1冊以上ですから、ものすごい量です。それなのに、本屋に行ったら自分の本がまったくなかった。誰も読んでくれないのになんのために描いてるんだと、自暴自棄になりましたね。やっぱり向いてないんだ、もう絵描きはやめたい、と。
すべてを変えてくれたのは『ごんぎつね』でした。絶望的な状態のときに、「これ描かない?」と偕成社の編集者が持ってきたんです。もちろん話は知ってたんですが、最初はどうやって描いていいのかわからなかった。それで、何かをつかめればと新美南吉の故郷に取材に行ったんです。初めての取材でした。『ごんぎつね』に出てくる川や山を見に行ったり、南吉の生家や養子先を訪ねたり、その土地の人に「赤い井戸ってなんですか?」と尋ねたり……あの絵は南吉のふる里の空気で生まれたんだと思っています。
1986年の絵本だから、もう20年以上前になりますが、これまでの仕事の中で一番思い入れのある作品といえば、やはり『ごんぎつね』ですね。
探し求めて見つけた、色鉛筆による画法

イラストレーターになってから、ペンや水彩、アクリル、果てはぬいぐるみまでつくって、いろんな表現方法を探し求めていたんです。
自分の求めていた画材はこれだ!と気付いたのは、木暮正夫さんの『虹のかかる村』(サンリオ)の絵を描いていたとき。もう絶版になっているのですが、ちょっと大人向けの作品で、亡くなった恋人の生まれ故郷を訪ねると、夜の駅は霧がいっぱいでしたって話でした。その霧を描いてるうちに、すごく気持ちよくなって……描きあげたころには、これが自分にもっともふさわしい画法だと思ったんです。色鉛筆は、乾くのを待たずに描き続けることができる、というのも、気質に合っていたのかもしれません。
最近は買いに行っていないのでわかりませんが、日本で手に入るほとんどの会社の色鉛筆を揃えていますよ。全部硬さや軟らかさが違うし、ブルーでも濃さ薄さが違いますからね。
……黒井健さんのインタビューは後編へとまだまだ続きます。(【後編】はこちら→)